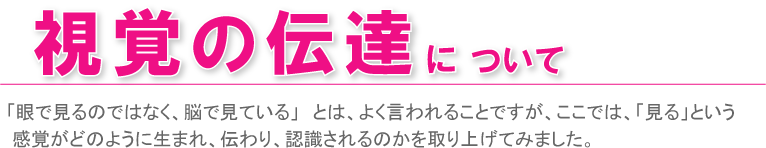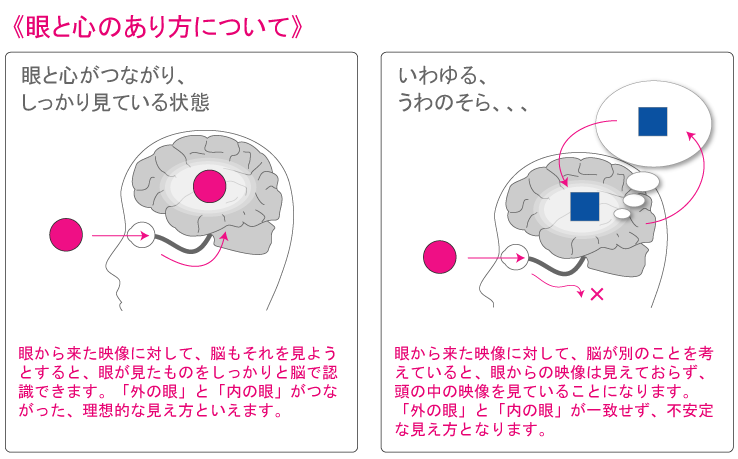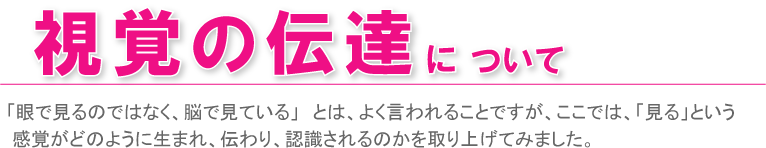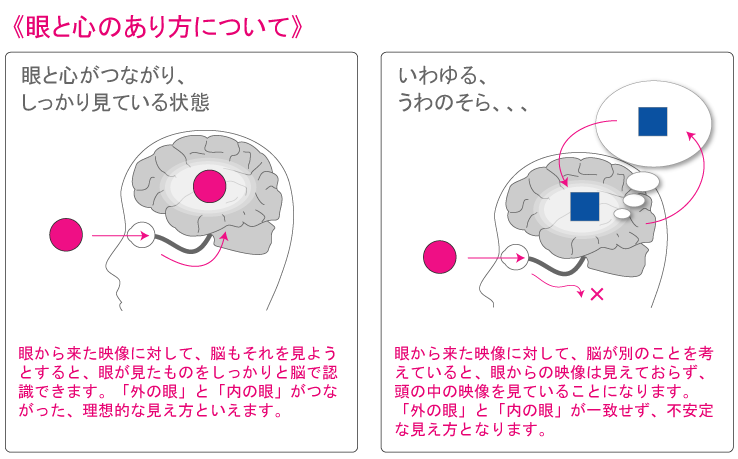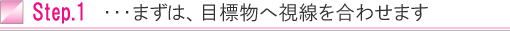
|
|
外眼筋の働きにより眼球運動を行い目標物に視線を合わせます。この時、映像を網膜の中心窩でとらえられるように位置調整ができることが必要で、左右の眼がバランスよくスムーズに動くことが重要です。
眼球運動に問題があると、ぼやける・ダブって見える・二重に見える・眼が疲れるなどの症状が起こることがあります。 |
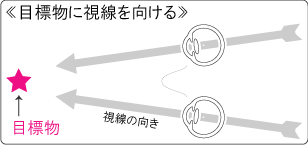 |
|
|
|
|
|
現在の眼鏡店では、眼位や眼球運動などを考慮した眼の測定やメガネ作りは、ほとんど行われていません。
しかし、この問題は非常に大事なことなので、当店では必要と思われるお客様には詳しく測定させていただき、その要素をメガネに含めたほうが良い場合には、そのお話もさせていただいております。
「眼が疲れる」、「見えるけど、見づらい」、「物が二つにダブって見える」、「距離感がつかみにくい」などの症状がありましたら、お気軽にご相談ください。 | | | | |
|
|
|
|
|
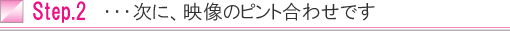
|
|
網膜の中心窩でとらえた映像も、ピンボケ状態ではきれいに見えませんので、目標物の距離に合わせて眼の焦点距離を調整する必要があります。
眼の屈折系は角膜と水晶体ですが、ここでは水晶体が、その厚みを変えて網膜上にピントの合った映像が映るように調節を行います。
カメラで言うなら、ウィーンウィーン とレンズが動いてピント合わせを行う行為にあたります。
わずかではありますが、外眼筋が作用して眼球の形や位置を微妙に変化させることにより、補助的にピント合わせを行うこともあると考えられています。
このピント合わせに不都合が生じる問題が、いわゆる「屈折異常」、「調節不足」といわれるものです。
水晶体を膨らませない状態で、遠くを見ている場合においてピントが合わないのが「近視」・「遠視」・「乱視」などです。
水晶体を膨らませて近くにピント合わせをしようと思ったときに、膨らみが不足してピントが合わない状態が「調節不足」、別の言い方をすると「老視(老眼)」と言うことになります。
|
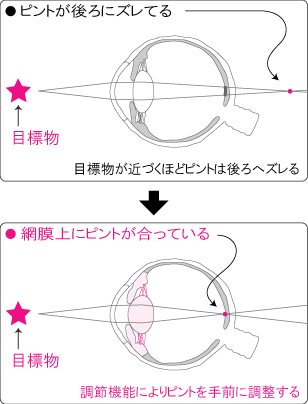 |
|
|
|
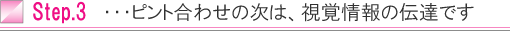
|
|
網膜に映った映像には、網膜上の視細胞が反応し、その情報は、「視束」から「視交叉」、「視索」、「外側膝常体」を経て「大脳後頭葉」にある「視中枢」に伝達されます。
ややこしい言葉が並びますが、簡単に言うと、眼から入った映像は、視神経を伝わり脳に届くということです。
この視覚の伝わる経路を「視覚伝導路」あるいは「視路」といいますが、少々ユニークな経路をたどります。
右眼の右側(耳側)視野と左眼の右側(鼻側)視野が左へ、右眼の左側(鼻側)視野と左眼の左側(耳側)視野が右へ伝わります。
その為、例えば右の「視束」で障害が起これば右眼の全視野不良、右の「視索」で障害が起これば、右眼鼻側・左眼耳側の視野不良が起こります。
ちなみに「視交叉」の疾患では、両眼耳側の視野不良が特徴となりますが、視交叉の中央部の障害では両眼鼻側の視野不良が起こります。
何がなにやら、理解しがたい話ですが、右の図を見ていただければ、なんとなくイメージしていただけるかと思います。 |
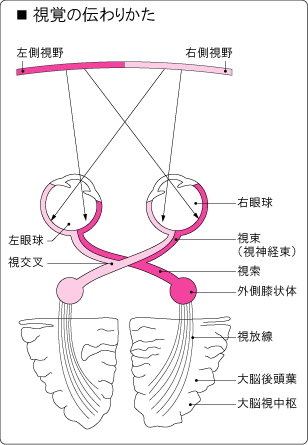 |