 |  | |
|
|
|
|
|
|
乱視とは、水晶体が調節を休止した状態にあるとき、平行光線がどこにも像を結ばない眼をいいます。(調節をおこなったとしても焦点を結びません)
遠く、近く、共に見づらくなります。 眼を細めたり、力を入れたりすると幾らか見やすくなりますが、完全なピント合わせを行うことはできません。
乱視には、「不正乱視」と「正乱視」があります。
「不正乱視」は、主として角膜疾患などにより角膜表面が凹凸になっているために像が不規則に焦点を結ぶむので、メガネレンズでの矯正はできません。 コンタクトレンズにより矯正可能な場合があります。
「正乱視」は、角膜(または水晶体)の湾曲が正しい球面になっていないために起こるもので、メガネレンズ、またはコンタクトレンズでの矯正が可能です。一般的に眼鏡店などで、「乱視のメガネ」などといわれる場合は、この「正乱視」のことです。
乱視ではない眼の場合、角膜(または水晶体)の湾曲は正しい球面をしています。(例えばバレーボールのようにです)
それゆえ下図のように光の要素が縦・横などの方向にかかわらず1点で焦点を結びます。
ところが、「乱視」の眼(正乱視)は、例えるならラグビーボールのように縦と横の湾曲(カーブ)が異なりますので、下図の場合ですと、縦の要素は屈折が強く作用し手前で焦点を結ぶのに対し、横の要素はそれより後ろで焦点を結びます。その結果、光が一点で焦点を結ばず、ピントの合った映像とはなりません。これは、見る距離にかかわらず同じことが言えます。
|
|
|
|
|
|
 |
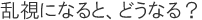 |
|
|
|
|
|
|
 |
遠いところも近いところも見づらくなります。
どのように見づらくなるかは、下図をごらんください。図の中の上段は「線」を見たときの状態、下段は「点」を見たときの状態です。
「a」は、屈折異常の無い「正視」の見え方です。すべての線、点、共にくっきり見えます。(モニター表示の関係上、線が不均等に見えてしまう場合があります)
「b」と「c」が「乱視」の見え方です。線は角度により見やすい線と見づらい線があり、点は、ある一定の方向にぼやけます。
学生さんで「b」タイプの乱視の方は、算数の時間に黒板に書いた足し算が、全部 引き算に見えてしまうということも起こり得ます。
実際には、近視や遠視が混ざっている場合が多いので、下図のような見え方にならない場合もありますが、角度や方向により見えたり見えなかったりする要素を含んだ眼ということです。
「d」は乱視のない「近視」または「遠視」の見え方です。角度・方向に関係なく均等にぼやけて見えます。
※ 「b」と「c」の見え方は、乱視の眼の一例です
| |
|
 |
単眼複視といわれる、片眼で見ても1つのものが2つに見える症状が起こることがあります。
「不正乱視」の場合、複雑な焦点の結び方をしますので、物が何重にもダブって見えることがあります。「正乱視」の場合も、偏ったぼやけ方をすることにより、二重にずれたように見えることがあります。
|
|
|
|
|
|
|
 |
眼精疲労が起こることがあります。
調節を行う(眼に力を入れる)と いくらか見やすくなるため、常に眼に力を入れて見ることが多くなります。 その結果、調節の努力が絶えず必要になり眼が疲れます。 いわゆる調節性眼精疲労です。 眼が疲れるだけでなく、頭痛や肩こり、全身のだるさなどが生じることもあります。
|
|
|
|
|
|
|
|
乱視の場合、視力測定で良い結果が出てしまうこともあり、
気がつかないこともよくあります。
「眼が疲れる」、「眩しさを感じやすい」、「眼が疲れる」、「頭痛・肩こり」などが
気になる方は、一度、眼の測定をされることをお勧めします。 |
|
|
|
|
|
|
 |
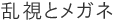 |
|
|
|
|
|
|
|
乱視も遠視の場合と同じく、視力不良と共に眼精疲労を生じることがありますので、メガネの装用が必要です。
乱視は、視力不良を実感しづらかったり、眼を細めたり、力をいれたりすることにより幾らか見やすくなります。そのため、メガネを装用しない方が多いのですが、眼にかかる負担は軽視できないものがあります。見づらくなくても一定以上の乱視がある場合には、眼鏡装用をおすすめします。 |
|