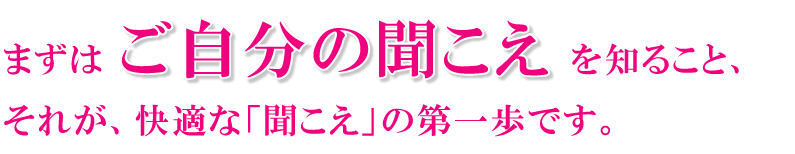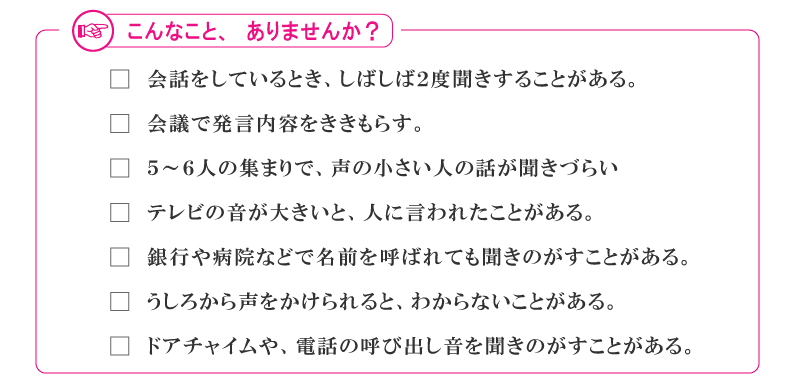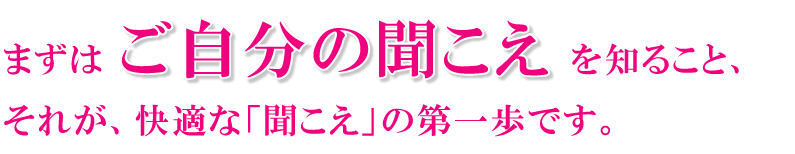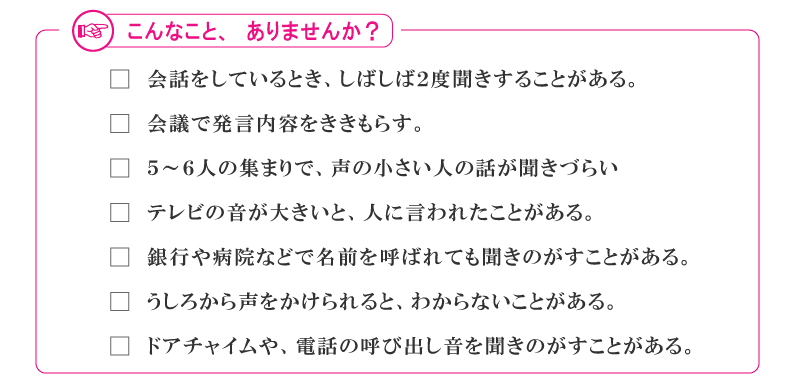|
|
|
|
まず、代表的なものとしては、「純音聴力検査(測定)」です。
皆さん一度はご経験あるかと思いますが、ヘッドホンをつけて「ピー」とか「プー、プー」とかの音が聞こえたらボタンを押す、あの検査です。 |
|
|
|
|
|
健康診断で行うのは簡易的なもので、ほんの短い時間で終わってしまいますが、通常は、125Hz ・ 250Hz ・ 500Hz ・ 1000Hz
・ 2000Hz ・ 4000Hz ・ 8000Hz の7種類の純音を用いて測定します。
測定内容は、それぞれの音がどのくらい小さな音が聞き取れるかを測定します。聴力に異常がないかどうか、そして異常がある場合には、どんな種類の音がどの程度聞こえないのかを判断できます。
補聴器販売店においては聴力測定をおこなっても、難聴などの診断をすることはありません。
測定したデータは、補聴器の音質調整を行うデータとして用います。
メガネの度数あわせみたいなもので、使用される方の聞こえの特性に補聴器からの出力音を調整することで最大限の聞き取り効果を目指します。
|
|
|
|
※ 純音について
純音とは正弦波(もっとも基本的で単純な波)で表される混ざりけのない音のこと、つまり最もシンプルな一種類の波長からなる音で自然界には存在しないものです。楽器や人の声など音が混ざり合ってできた音なので純音とはいえません。 |
|
|
|
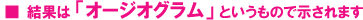 |
|
|
|
| 「純音聴力検査(測定)」をうけて、その結果として出てくるのが、右の図のような「オージオグラム」というものです。 |
|
| 横軸が「周波数」で、音の高さを表わします。125Hzが低音、右に行くにしたがって高音になります。 |
|
| 縦軸が「音圧レベル」で、音の強さ(大きさ)を表わします。数字が大きくなるほど強い(大きい)音になります。0dBは無音ではなくて、健聴者が聞き取れる一番小さな音です。 |
|
| ヘッドホンをつけて気導経路で測定したものが○(右耳)、×(左耳)で記入されます。 「 [ 」や「 ] 」などの表示は骨導検査(測定)の結果です。 |
|
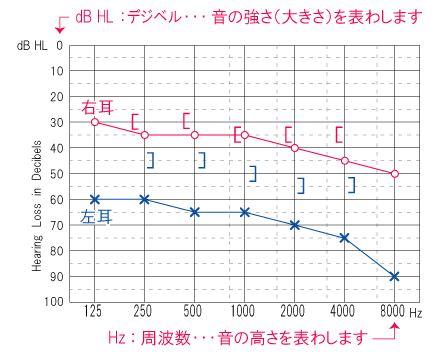
| ※ |
補聴器の分野では、右を「赤色」、左を「青色」であらわす決まりがあります。
|
|
見方としては、グラフが上にあるほど聞こえが良く、下にあるほど聞こえが悪いことになります。
例えば、図中の右耳、低音の「125Hz」は30dBの大きさで聞こえますが、高音の8000Hzでは、少し大きめの50dBでないと聞こえないという結果を表わしています。
また、左耳は右耳に対してかなり聴力が落ちている結果が出ていて、8000Hzの高音では、90dBもの強大音でないと聞き取れない状況が示されています。 |
|
|
|
|
|
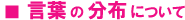 |
|
| 右のオージオグラムの中にあるピンクで塗りつぶした領域は、スピーチバナナといって、標準的な言葉の分布する領域をあらわしたものです。 |
|
| 言葉の強さと高さから考えると、日本語の場合は大体この領域に日常会話が含まれてくると考えられています。 |
|
分布領域がバナナの形に似ているので「スピーチバナナ」と呼ばれています。 |
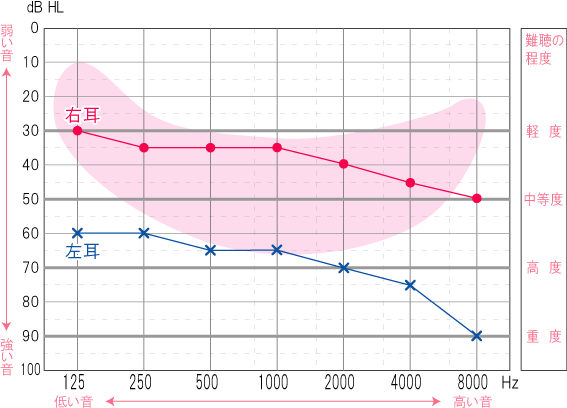 |
|
このスピーチバナナ領域より下に聴力グラフが位置している場合には、日常会話に不便が生じている可能性が大きいと考えられます。 実際には1つの言葉の中にも複数の周波数要素が含まれていますし、周波数以外の要素からも音声判断を行っています。また、話者によっても声質の高低があります。 |
|
また、聴力グラフとして示されている値は、音を感じ取れるぎりぎりの小さな音ですから、そこから少し大きめな音でないと言葉としの聞き取りは難しいと思われます。
そのため、上図のような表によって言葉の聞き取り具合を容易に判断することはできませんが、おおよそのイメージとして載せてみました。 |
|
|
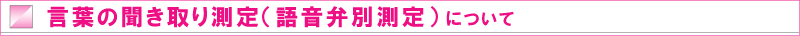 |
|
|
|
|
|
標準純音聴力測定では、どのくらい小さな音が聞き取れるかを測定しましたが、「語音弁別測定」は、言葉の聞き取りを測定するものです。 |
|
|
|
|
|
測定方法は、「ア」、「キ」、「シ」、・・・・などの言葉を順番に聴いていただき、聴こえたままに用紙に記入していただきます(または、言い返していただきます)。聴いていただいた言葉の数に対していくつ正解したかによって正解率を求めます。 20語のうち、全問正解なら正答率100%、10語正解なら50%といった具合です。 音の大きさを変えて複数回行い、最高の正解率を求めます。
会話をするためには、音を感じるだけでなく言葉を聞き分けることが必要です。 「語音弁別測定」は、言葉を聞き分ける力を測定することで、普段の会話における不自由さを推測したり、補聴器を装用したときの効果を予想したりすることが出来ます。 |
|
|
|
|
|
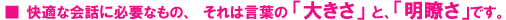 |
|
|
|
|
|
感音性難聴などで言葉の鮮明さが失われている場合、「音として聞こえているが聞き分けが出来ない」ということが起こります。これは、聴覚神経などの感音系器官に問題があるため起こると考えられるもので、聞き取った言葉の輪郭がぼやけていることに原因があると言われています。いわゆる「言葉がハッキリしない」というものです。 言葉のぼやけ、、、 つまり、明瞭度が落ちている場合、補聴器で音を大きくしても、思うように聞き取りが向上しない場合があります。 |
|
|
|
|
|
例えば、「あ」という言葉を聞いたときの状態を、下にイラストで表してみました。 |
|
|
|
|
|
| ● |
言葉が小さいことで聞こえにくい場合には、補聴器で大きくすることにより、よく聞こえるようになります。 |
|
|
|
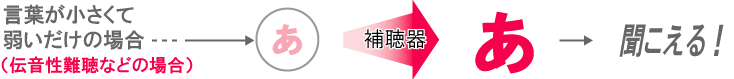 |
|
|
|
|
|
| ● |
言葉が小さいだけでなく明瞭性も落ちている場合は、補聴器で大きくしても言葉の輪郭がハッキリしないために言葉が分かりにくい場合があります。 「聞こえてはいるけど何を言っているのか分からない」といった状態になります。 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
これを視覚にたとえるならば、 「 小さくて見えないけど、拡大鏡で文字を大きくすれば良く見えるようになる状態 」が語音弁別が良い場合で、 伝音性難聴では、このような状態が多いように思われます。 |
|
|
|
|
|
これに対して、「 小さいうえに文字のピントがぼやけているため、拡大鏡で大きくしても今ひとつスッキリ見えない状態 」ですと語音弁別の成績はあまり良くありません。拡大することにより、いくらか見やすくなりますが、ピントのぼやけは解消されていませんので、スッキリした見え方とはならない状態です。 感音性難聴の場合には、このような状態にあるのではと考えられます。 |
|
|
|
|
|
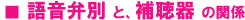 |
|
|
|
|
|
語音弁別の測定結果をみることにより、補聴器の装用効果をある程度判断することができます。
測定結果が良好な場合には、補聴器の装用当初から効果を感じることが出来る場合が多く、測定結果が良好でない場合には、補聴器装用の効果を実感しづらい場合もあります。 |
|
|
|
|
|
ただし、測定結果が悪いからといって、補聴器を使っても意味が無いというわけではありません。
例えば、会話の聞き取り率 30%くらいの方が、補聴器をつけても60%程度にしか改善しないと聞くと、なんだか物足りなく感じるかもしれませんが、それでもかなり不便さは改善されるものです。
少々聞き取りにくさがあっても、周りの方が多少ゆっくりめに会話をすることで、普段の会話に関しては結構不自由なく行うことができるようになる場合もあります。
また、しばらくして補聴器の音に慣れてくると、聞き取り率が向上してくることもあります。 聴覚機能が戻るわけではありませんが、明瞭性が低下した状態でもそれをうまく解釈しながら聞き取るのが上手になるのではないかと思われます。
|
|
|
|
|
|
場合によっては補聴器による「言葉の聞き取り改善」がほとんど得られないこともあるのですが、今まで聞こえなかった音が耳に届くようになるということだけでも大きな意味が生まれることがあります。 たとえば散歩中に、後ろから来た車の音が聞こえるということはとても大事なことですからね。 |
|