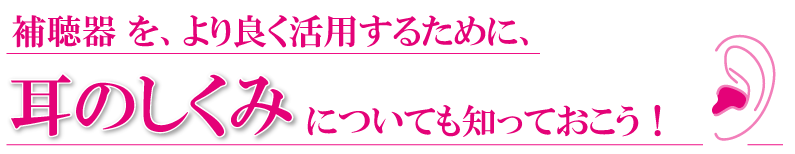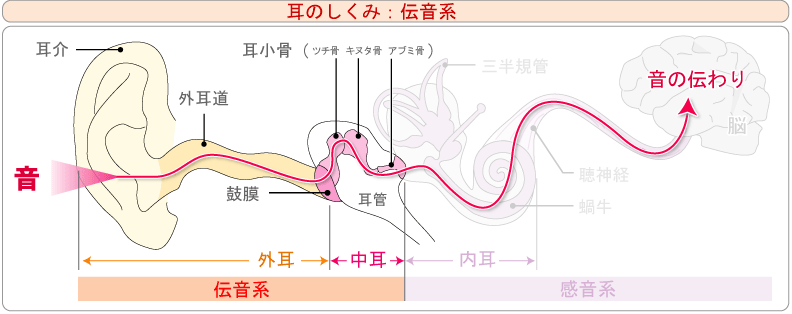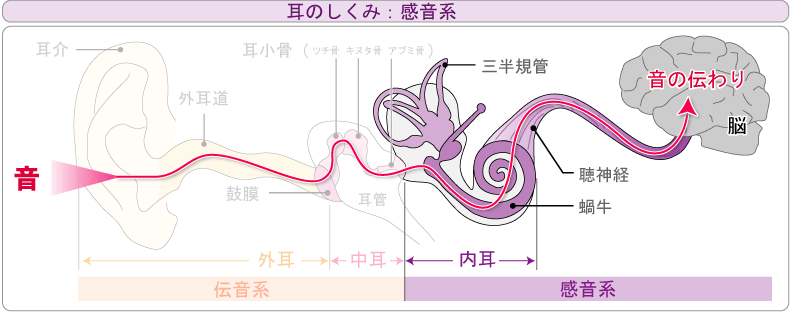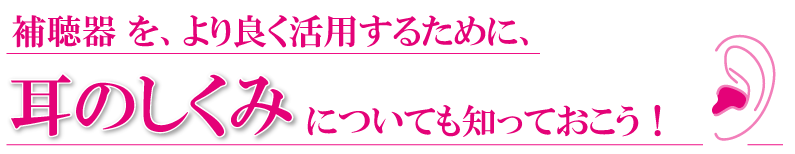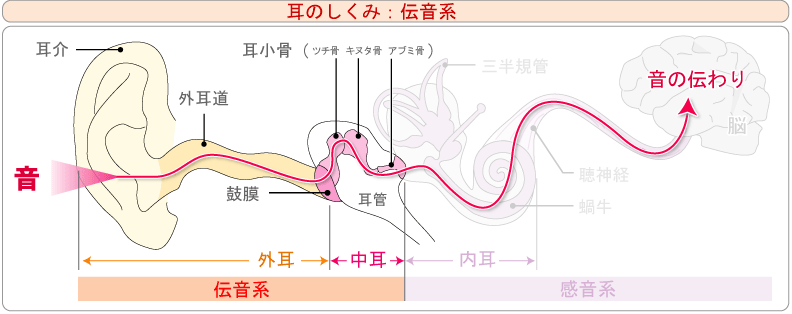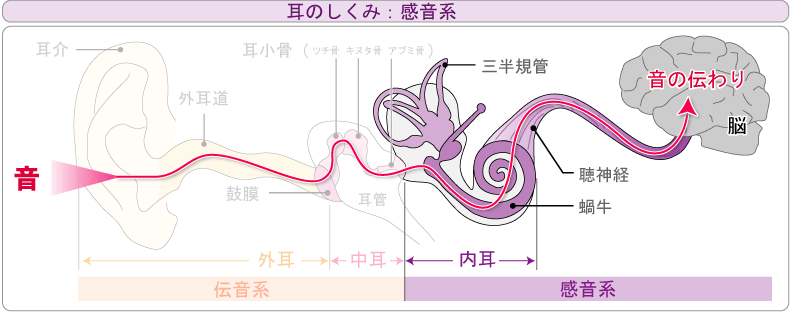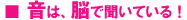 |
| |
| 一般的に、音は耳で聞いていると思われていますが、実際に音を認識して聞いているのは脳です。
耳は、振動を音として、その「高低(周波数:Hz)や強さ(音圧レベル:dB)などの特性」を感じているのであって、言葉などを認識して聞き分ける能力はありません。
脳に届けられた音の情報は、「周波数・音圧レベル・波形特性」などがデータ化されたもので、そのデータを脳に蓄積された、音のパターンや言葉のサンプルなどと照らし合わせてようやく「意味を理解して聞く」ということができるのです。
普段なにげなく交わす会話ですが、脳の中ではものすごい速さで、音の分析・照合・認識・理解 を 絶えず行いながら会話をしているのです。 |
|
|
|
長年のあいだ聞こえづらく、脳に正確な音の情報が届いていなかった方が、補聴器をつけて音を大きくしたからといって、脳で行う能力がすぐに以前と同じレベルで発揮できるかというと、そう簡単にはいきません。 時間をかけて耳と脳の連係を慣らしていくことが必要です。 |
|
|
|
ましてや 感音難聴の場合は、音の情報がいくらか不明瞭に変化してしまう傾向がありますので、脳に収納してある かつての言葉のサンプルと食い違いが生じてしまいます。「き」を「い」と聞き間違えてしまったり、言葉として認識できないといった場合もあります。
補聴器の効果が十分に発揮されるまでには それなりの期間を要することになります。 |
|
|
|
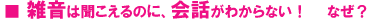 |
|
|
|
まわりの騒音などは、脳内での正確な「分析照合処理」をそれほど必要としません。言い換えると、音を聞き分ける必要がないということです。 そのため、音として感じただけで
「 聞こえた 」 となります。
それに対して会話の場合は、音として感じた後、その音がどんなものかを分析し、どんな言葉なのか照合して認識されなければ 「 聞こえた 」 とはなりません。同じ
「 聞こえた 」 といっても、雑音と会話では全く別次元のものなのです。
「 補聴器をつけたら、まわりの雑音はよく聞こえるけど、肝心の会話が聞き取れない 」というのは、よく生じる問題ですが、これは実に当然のことで、この問題を乗り越えるには、「販売店」はもとより、「補聴器を使うご本人様」と「その周りの方々」にも、聞こえと補聴器の特性をご理解いただき、前向きにじっくりと取り組む必要があります。 |
|
|
|
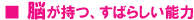 |
|
|
|
脳が持つ優れた能力で、「不要な音を消し去る」という機能があります。
たとえば、 レストランなどの騒がしいところで会話をする場合、周りの人たちの会話も混ざってしまい非常に聞きづらい状態となりますが、私たちは無意識のうちに相手の話に集中して、他の音は聞き流しています。 この、「不要な音を聞き流す」という作業は非常に高度なもので、補聴器でこれを実現することは容易なことではありません。
最近の補聴器には「雑音抑制機能」がついているものもありますので、周りの「ザワザワ」した感じをある程度抑えることは可能です。しかし、聞きたい相手の言葉と、隣の席で話している言葉では音響特性も似てますので、どちらを抑制すべきかを判断することは困難です。 場合によっては隣の人の会話を聞きたい時もあるわけですし、聞き手の意識の中の問題ですからね。
補聴器の特性を調整することで、届く声の大きさや方向などから判断して目標を絞ることもできますが、状況により変化する目標に対して臨機応変に対応することは、やはり非常に難しいことです。 |
|
|
|
| 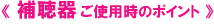
補聴器を装用しても効果を感じにくい場合、その多くは「感音性難聴」などにより言葉の明瞭性が思うようにあがらなかったり、耳と脳の連携がうまくできていないことに多くの原因があるように思われます。
多くの場合、補聴器の音量設定が控えめになっていますので、これを使用状況を見つつ上げていくことも必要です。 | |
|
|
|
|
いずれの場合も結果をすぐに求めるのではなく、気長にあせらず補聴器と付き合っていくことが大切です。補聴器を通した音に慣れるまでには期間を要するものです。
また、いろいろと音の特性を変えることも出来ますので、お気軽にお申し付けいただき 状況に応じて音質調整を行っていくことも大事なことです。
そして、お話をされる相手の方が、話し方を ほんの少し変えるだけで、聞き取りがぐっとよくなることもありますので、皆で協力して改善していくことが必要だと私たちは考えています。 |
|
|