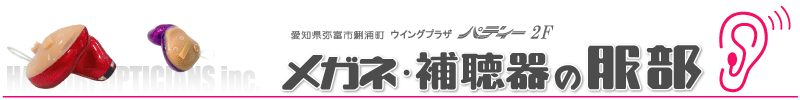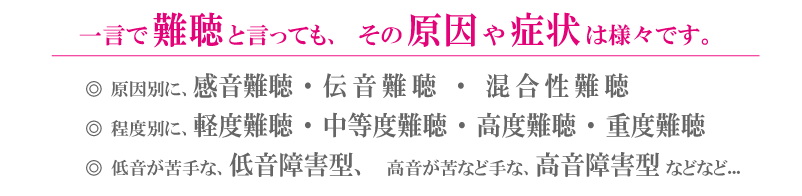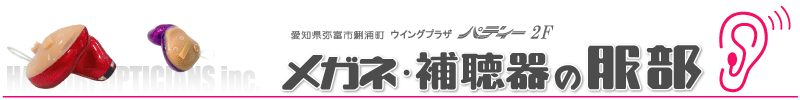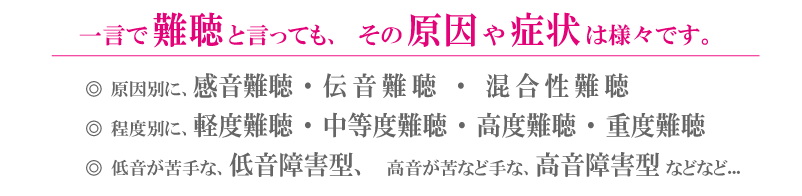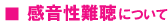 |
|
内耳以降の感音器、つまり音を感じる部分になんらかの障害があるために起こる難聴です。
この難聴の代表が加齢とともに聞こえにくくなる聴覚障害です。
薬物や長時間にわたり騒音下にいることが原因で起こる聴覚障害もこれにあたります。単に聞こえにくいだけでなく、音がひずんで聞こえる場合も多く、言葉の聞き違いなどが起こります。
感音難聴では、原因となる故障部位が、内耳の感覚細胞か聴神経か脳中枢かによって、聞こえの悪くなりかたに大きな差があります。そのため補聴器の効果も、人によってはかなり正常耳に近づけることが可能な場合もありますが、満足のいく充分な効果がみられない場合もあります。
《感音難聴の主な種類》
「突発性難聴」「騒音性難聴」「老人性難聴」「音響外傷による難聴」「薬物中毒による難聴」「メニエル氏病による難聴」など。 |
|
|
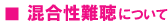 |
|
伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こるタイプの難聴です。
補聴器の効果に関しては、難聴の原因が伝音系と感音系のどちらの割合が多いかによって異なります。
伝音難聴分が多い場合では大きな効果が期待できますが、感音難聴分が多い場合では上記のとおり効果に差がみられます。 |
|
|
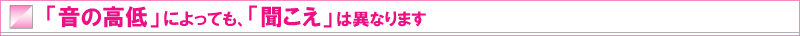
音には、低い音や高い音などいろいろな種類があります。これは音の周波数帯域の違いによるものですが、この周波数帯域(音の高低)の違いにより、聞こえの程度も異なることが一般的です。
代表的なものに、低い音域が聞きづらい「低音障害型」、全域の音が等しく聞きづらい「水平型」、高い音域が聞きづらい「高音障害型」などがあります。
加齢とともに生じる難聴の場合は高音障害型になることが多く、言葉を聞き取るうえで大切な子音部分の聞こえが悪いため、「相手の声は聞こえるが、聞き間違いや聞き分けがしづらい」といった症状がよくみられます。
|
|
|
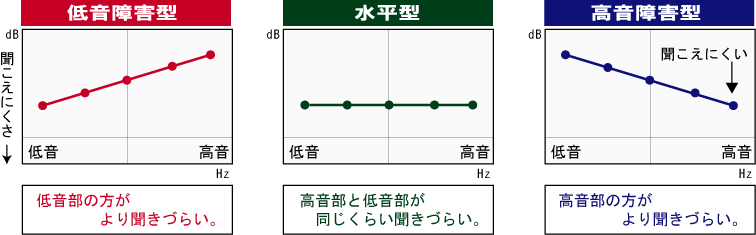 |
|
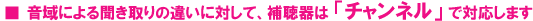 |
|
聞こえは、音の高低によって異なるのが一般的なので、補聴器で音を大きくする際には音の高さによって増幅率を変える必要があります。
そのため、補聴器では外から入ってきた音をいくつかの音域ごとにわけて増幅するシステムになっています。この音域をわける数をチャンネル数といい、現在のデジタル補聴器では2チャンネルから多いもので48チャンネルくらいまであります。 |
|
2チャンネル・4チャンネル・8チャンネルのイメージを下図にあらわしてみました。
図中の薄い紫色のグラフが聞こえの状態をあらわしています。この場合の聞こえの程度は、低音が中程度、中間音は少しだけ、高音はかなり聞こえづらくなっている状態です。 グラフは下にあるほど聞こえにくく、上にあれば聞こえやすいことになります。薄黄色の領域が聞こえの正常範囲です。 薄黄色の領域内の上の方で、横一列に揃うグラフとなっていれば理想の聴力だといえます。 |
|
| 上向きのピンクの矢印が、補聴器による音の増幅をあらわしています。 2チャンネル型は当然ながら2ヶ所で聞こえを上に引き上げることになります。 8チャンネルでは、8つの矢印で引き上げています。 |
|
そして、濃い紫色のグラフが補聴器により増幅された後の理論上の聴力を表しています。
2チャンネル型では押し上げ箇所が2ヶ所ですから、思うように「聞こえ」を平均化することができませんが、4チャンネルでは何とか正常領域に収めることができていますが、音域ごとの聴力は平均化されていません。8チャンネルは、ほぼ平均化することができています。 |
|
| 実際には、音を大きくすれば必ず聞こえるようになるとは限りませんので、補聴器装用後の聴力が必ず下図のようになるというわけではありませんが、イメージとして見ていただけたらと思います。、 |
|
|
|
|
|