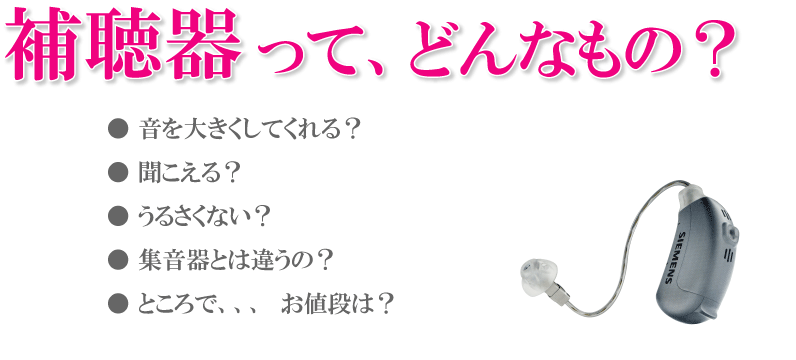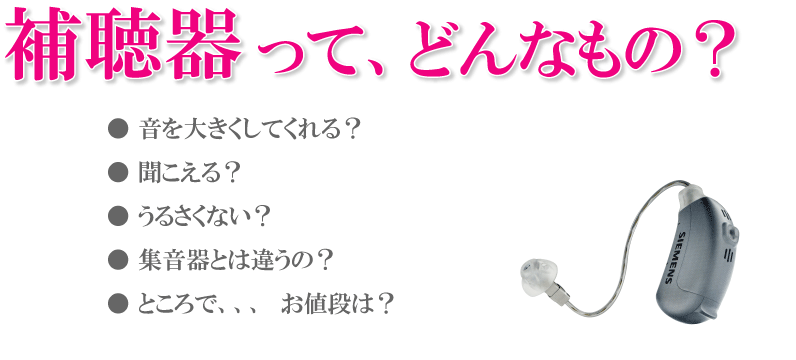| 「聞きづらい」と一言でいっても、どんな種類の音が、どの程度聞きづらいのかは、その方のお耳の状態によって異なります。 |
|
|
|
例えば、音の高さの違いによっても聞こえ具合は変わります。 |
|
|
|
音の中には「低い音」から「高い音」までいろいろあります。言葉の中でも「ア」、「ウ」、などは低いほうですが、「キ」、「シ」、「チ」などは高めの音声です。 この音の高さを表わすのに「周波数:
Hz (ヘルツ)」という単位を使いますが、この周波数の違いにより聞こえが異なってくるのです。 |
|
詳しくはコチラ→「音について」 (※ 新規ページで開きます) |
|
そこで補聴器は、 |
|
|
|
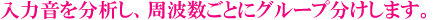 |
|
|
|
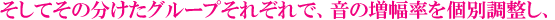 |
|
|
|
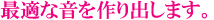 ※ これをマルチチャンネルシステムといいます ※ これをマルチチャンネルシステムといいます |
|
|
|
たとえば、高音だけが聞き取りにくい方が補聴器を装用する場合、主に高音グループを増幅し、低音グループは増幅せずに出力します。 |
|
|
|
あるいは、中間音域が聞き取りにくい場合は、低音・高音はあまり増幅せずに、中間周波数域を主に増幅します。 |
|
|
|
聞こえてる音域まで大きくしてしまうと、「うるさい!」となってしまいますので、その方の聞こえに合わせて音質調整がなされます。 |
|
|
|
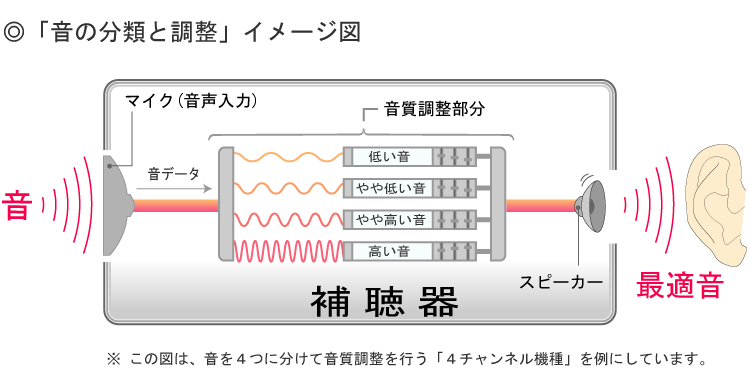 |
|
|
|
このような、音域に合わせての増幅率の設定は、あらかじめ私たち販売店のスタッフが補聴器にプログラムするわけですが、それ以後は、 |
|
|
|
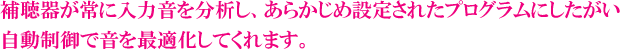 |
|
|
|
※ 記載内容はデジタル方式の補聴器を想定しています。 |
|
|
|
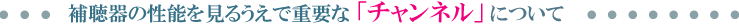 |
|
|
|
補聴器の分野では、この、分類された音のグループの数を「チャンネル」という言葉で表します。4つのグループに分ける場合は「4チャンネル」、12グループなら「12チャンネル」と表現します。 |
|
|
|
この「チャンネル」の数は、補聴器の機種によって異なり、補聴器の基礎的な性能を判断するための重要ポイントです。スタンダード機種で2〜4チャンネル。高性能機種では16チャンネルもあります。 |
|
|
|
チャンネル数が多いほど、装用者の聞こえに合わせたきめこまやかな音質調整が可能となり、「オススメ!」と言うことになるのですが、チャンネル数の多い機種ほど高額なご予算が必要になってしまいます。 |
|
|
|
どんな選択をすればいいのか迷ってしまうと思いますが、
一般的な聴力特性の方でしたら、4〜8チャンネルくらいあれば十分調整可能な場合が多いです。
あとは、価格とのバランスを考えつつ、騒々しい所で使用することが多い方や、聞き逃しが許されない方の場合はチャンネル数の多いものを。そうでなければ、ほどほどのもので、ということになります。 |
|
|
|
 |